1位

2021年11月29日
2021年12月22日労災について
こんにちは。神奈川県福祉共済協同組合の蝦名です。
業務中の事故や通勤途中の事故によって被害を負った場合などに、労働者本人や遺族の生活を守る「労災保険」。
基本的に、企業は従業員を1人でも雇えば労災保険に加入しなくてはならず、保険料は企業が全額支払う必要があります。
今回は、労災保険の労災保険料の金額を算出する方法についてのお話です。
労災保険の負担割合や、申告・納付で知っておきたいポイントなどもご紹介します。
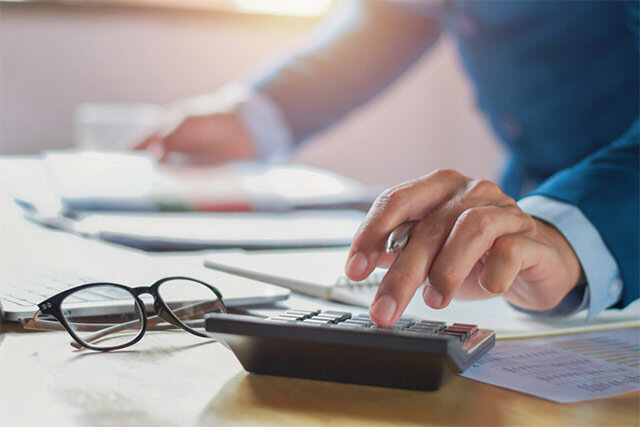
労災保険とは、業務中や通勤途中によりケガや病気になった場合や障害が残った場合、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度で、正式には「労働者災害補償保険」と言います。
雇用保険とあわせて「労働保険」とも呼ばれています。
労働者本人はもちろん、その後の遺族の生活を守るための公的保険制度の一種で、労働者を1人でも雇っている事業者は加入義務があります。
労働者を1人でも雇用している事業者。
(ただし、官公署の事業のうち非現業のものや、国の直営事業所、船員保険被保険者は労災保険の対象外です)
正社員、パート、アルバイト、派遣労働者、日雇い労働者などすべての労働者が対象です。
(派遣労働者は派遣元の事業所が加入します)
なお、事業主本人や役員、請負で働く一人親方などは労災保険の対象外ですが、任意で加入できる特別加入制度もあります。
会社を設立し、労災保険の適用事業所になったときは、労働(労災・雇用)保険の対象事業所であることを届け出たうえで、当該年度末までの概算保険料の申告・納付を行う必要があります。
労災保険については、所轄の労働基準監督署に、下記の3点を提出します。
提出期限は、保険関係が成立した翌日から起算して10日以内となっています。
労災保険について、詳しくは「労災保険とは?わかりやすく条件や補償内容、手続き方法を解説!」でもご紹介しています。
あわせてご確認ください。

先述の通り、労働者を1人でも雇用している事業者は労災保険に必ず加入する義務があり、その保険料は全額事業者が負担します。
労災保険料は、前年度に全従業員に支払った賃金総額(事業主や法人役員など労災保険に加入できない人を除く)に、事業者ごとに定められた労災保険料率を掛けて計算します。
新たに設立した会社の場合は、その年度の末日までに支払う予定の賃金総額で計算します。
<労災保険料計算式>
労災保険料=全従業員の前年度(1年間)の賃金総額×労災保険料率
全従業員の賃金総額とは、労働の対象として支払うすべてのものをいい、基本給や賞与だけでなく、通勤手当、定期券・回数券、残業手当、休日手当、扶養手当、家族手当、在宅勤務手当なども含まれます。
ただし、役員報酬をはじめ、出張・宿泊費等の立替経費の実費弁償分や傷病手当金、結婚祝金、会社が全額負担する生命保険の掛金などは含まれません。
近年在宅勤務の方も増えていますが、自宅と会社との間の交通費については、労働契約上の役務提供地によって扱いが異なります。
契約上「自宅」が役務提供地の場合は、業務として一時的に会社に出社する際の交通費は実費弁償となり、賃金に含めません。
反対に、「会社」が役務提供地の場合は、通勤手当の扱いとなり、賃金に含めます。
労災保険料率は、林業が6%、金属鉱業は8.8%、建築事業は0.95%、食料品製造業は0.6%、卸売業・小売業は0.3%といったように、厚生労働省「労災保険率表」によって事業種別に決まっています。
※記載の労災保険料率は2021年12月時点のものです
労災保険料率は事業内容を同じくする集団における過去3年間の労働災害の発生率をもとに決定されています。
労災保険料を計算する際には、まずご自身の企業がどの事業の種類に分類されるかを確認する必要があります。
実際に、労災保険料の計算方法を見ていきましょう。
従業員数30人、平均年収450万円のタクシー会社(交通運輸事業)の場合
労災保険料率:0.4%(2021年12月現在)
賃金総額:450万円×30人=1億3,500万円
労災保険料の計算式は【賃金総額(1億3,500万円)×労災保険料率(0.4%)=54万円】となり、この事業者の労災保険料は54万円となります。
計算時に小数点以下が発生した場合は、1円未満は切り捨てとなります。
ただし、労災保険と雇用保険の確定賃金が同額の場合、別々に計算して切り捨てるのではなく、労災保険と雇用保険の保険料率を合算して賃金総額に掛けてから、切り捨ててください。

労災保険の保険料は、保険年度(毎年4月1日〜翌3月31日までの1年間)ごとに概算の保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっています。そのため、前年度に納付した概算の保険料と確定の保険料に差額が生じた場合は、新年度の概算保険料から差額を調整したうえで納付する必要があります。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日〜7月10日までに行わなくてはいけません。
その際に、下記の様式を作成して提出します。
労災保険料率は過去3年間の労働災害の発生率をもとに決定されるため、3年ごとに保険料率の見直しがされます。
申告時においては、最新の保険料率を確認してください。
なお、労災保険とともに雇用保険の納付も合わせて必要となりますので、注意しましょう。
労災保険と雇用保険はそれぞれ別に給付を行っていますが、保険料の徴収は原則、一体のものとして取扱われます。
また、労災保険料を申告する際には、あわせて「一般拠出金」の申告・納付も必要となります。
一般拠出金とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるために負担するもので、労災保険料を支払う全事業者が支払うものです。
一般拠出金率は業種を問わず一律で、賃金総額に1,000分の0.02(0.002%)を掛けて算出します。
万が一労災事故が発生し、制度を利用して補償を受ける際は、労災の申請が必要となります。
労災の申請手続について、詳しくは「労災の申請手続きの流れをチェック!注意点や必要書類も確認」でご紹介しています。
こちらもあわせてご覧ください。
業務中や通勤途中に怪我や病気、障害、あるいは死亡した場合に、保険給付を行う制度「労災保険」。
労働者を1人でも雇っている事業者は、法律の上で加入義務があります。
労災保険料の計算方法は以下の通りです。
労災保険料=全従業員の前年度(1年間)の賃金総額×労災保険料率
前年度に全従業員に支払った賃金総額(事業主や法人役員など労災保険に加入できない人を除く)に、事業者ごとに定められた労災保険料率を掛けて計算します。
労災保険は年度更新が必要となり、毎年6月1日〜7月10日までに手続きを行わなくてはいけないため、失念しないよう注意しましょう。
社労士または労働基準監督署に確認し、適切な手続きをとってください。
会社の福利厚生として、役員や従業員のための労災の上乗せ補償を準備しておくと安心です。
神奈川県内の中小企業や個人事業主の方は、神奈川県福祉共済協同組合の傷害補償共済Ⅲもぜひご参考ください!