1位

2021年11月29日
2021年09月27日労災について
こんにちは。神奈川県福祉共済協同組合の蝦名です。
「仕事でケガをしたら労災の対象」ということは知っていても、具体的な条件や内容はまではわからないという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、労災保険とはどんな内容の保険なのか、改めてわかりやすく解説します。
労災事故が起こったときに焦ってしまわないよう、労災保険の給付内容や手続き方法、申請時の注意点などを知っておきましょう。

労災保険とは、業務上の事由または通勤途中の事故によって負傷、疾病、高度障害、死亡等の被害を負った労働者本人やその遺族の生活を守るための公的保険制度の一種です。
よく「労災」と呼ばれていますが、正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。
たとえば労働災害によるケガや病気のために医療機関にかかるための費用や休業時の補償、高度障害が残ってしまった場合の障害補償などがさまざまな補償があります。
労働者を1人でも雇用している事業者は、労災保険に必ず加入することが法律で義務付けられており、保険料は100%事業者が負担します。
労災保険の対象は、雇用形態や勤務日数・時間に関わらず、正社員、パート、アルバイト、日雇い、季節雇用などすべての労働者です。
派遣社員の場合は、派遣元の事業所が加入します。
企業の代表者や役員、一人親方や個人事業主などは「労働者」に当たらないので加入対象とはなりません。
ただし、申請により任意で労災保険に加入できる特別加入という制度もあります。
また、労災事故によっては、労災保険で補償される以上の高額賠償を請求される可能性がありますし、慰謝料の請求に対しては労災保険で対応はできません。
そのような場合に備えて、中小企業や個人事業主の方は「労災上乗せ保険」に加入することをおすすめします。
神奈川県福祉共済協同組合でも、さまざまな共済制度を用意しています!
もし、貴社の労災対策でご心配がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
資料のご請求もお待ちしています。
労災保険が適用される労働災害は、業務に起因する「業務災害」と通勤時に起こる「通勤災害」の2種類に大別されます。
業務時間内や業務を原因として発生したケガ、病気、障害、死亡など。
業務災害と認められるためには、業務遂行性(業務中に起きた事故であること)、業務起因性(業務が事故の原因となったか)の両方の条件を満たさなければなりません。
【業務災害が認められる例】
また、就業先が複数ある方(複数事業労働者)に対して、全就業先の負荷を総合的に評価し労災の判定を行う「複数業務要因災害」が加わりました(2020年9月以降に発生した事故が対象)。
業務上の負荷(労働時間やストレス)によって生じた脳・心臓疾患や精神疾患などについて1つの就業先のみの評価では業務災害と認められない場合に、複数の就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。
なお、複数事業労働者であっても、1つの就業先のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまでどおり「業務災害」として取り扱われます。
通勤中に起こったケガや病気、障害、死亡など。
通勤災害として認められるには、通勤中の条件を全て満たす必要があります。
【通勤中として認められる条件】
通勤の中断・逸脱を行った場合、その間やその後の移動は通勤として認められませんが、日用品の購入、通院、介護など「日常生活上必要な行為」をやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として取り扱われます。
労災保険の給付は7種類あり、「そのほかの給付」も合わせると8種類あります。
給付額は給与や賞与の金額をもとに計算され、給付の種類や災害内容の程度によって決まります。
業務災害に対する給付は○○補償給付、通勤災害に対する給付は○○給付、複数業務要因災害に対する給付は複数事業労働者〇〇給付という名称で区別されており、給付額は以下のとおりです。
労働災害によるケガや病気が治癒するまでの費用(医療費)が給付されます。
労災病院での受診は自己負担なしで受けられます。
給付額:治癒までに必要な療養または医療費の全額
労働災害による傷病によって仕事を休業した日が4日以上続いた場合に給付されます。
休業してから3日間は待期期間とされ、業務災害の場合は事業主が休業補償を行う義務を負います。
給付額:休業1日につき給付基礎日額の80%相当(休業(補償)給付として給付基礎日額の60%、休業特別支給金として給付基礎日額の20%)
労働災害による傷病によって後遺障害が残った場合の補償です。
障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合は年金、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合には一時金として給付されます。
給付額:障害等級第1級から第7級の場合は、障害(補償)年金として給付基礎日額の131日〜313日分と、障害特別支給金として159万円~342万円、障害特別年金として131日〜313日分
障害等級第8級から第14級の場合は、障害(補償)一時金として給付基礎日額の56日~503日分と、障害特別支給金として8万円~65万円、障害特別一時金として算定基礎日額の56日~503日分
労働災害で労働者が死亡した場合、遺族に対して年金または一時金が給付されます。
労働者の死亡当時、労働者の収入によって生計を維持していた遺族(妻以外の遺族は一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態の条件を満たした方)が対象の遺族(受給権者)となります。
給付額:受給権者がいる場合は、遺族(補償)年金として遺族の人数などに応じ、給付基礎日額の153日~245日分、遺族特別年金として算定基礎日額の153日~245日分、遺族特別支給金として遺族の人数にかかわらず一律300万円
受給権者がいない場合、または受給権者が受給権を失権し他に受給権者がいない場合かつすでに支給された年金の合計額が1,000日分に満たない場合は、遺族補償一時金として給付基礎日額1,000日分(既に支給額がある場合は差し引いた額)、遺族特別一時金として算定基礎日額の1,000日分(既に支給額がある場合は差し引いた額)、遺族の数にかかわらず一律300万円(受給権者がいない場合のみ)
労働災害で労働者が死亡した場合、葬祭を行う人に対して葬儀を行うための費用として給付されます。
給付額:31.5万円+給付基礎日額の30日分(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)
労働災害による傷病が特に重く、事故から1年6ヵ月を過ぎても治癒(症状固定)しない場合、傷病等級第1級から第3級に該当する障害が残った場合に給付されます。
給付額:傷病(補償)年金として給付基礎日額の245日〜313日分、傷病特別支給金として100万円〜114万円、傷病特別年金として算定基礎日額の245日〜313日分
障害(補償)年金と傷病(補償)年金の受給者のなかでも特に障害の程度が重い障害等級第1級と第2級の精神神経障害や胸腹部臓器の障害があり、現に介護を受けている場合に給付されます。
給付額:常時介護の場合は介護の費用として支出した額(月額上限171,650円)、親族などによる介護の場合、介護支出が73,090円以下の場合は月額73,090円
随時介護の場合は前者の上限85,780円、後者36,500円
(令和3年4月時点の金額です。最新の金額は厚生労働省ホームページをご確認ください)
そのほか「二次健康診断等給付」などがあり、定期健康診断等で脳・心臓疾患の所見があった場合、必要な二次健康診断や特定保健指導が給付されます。
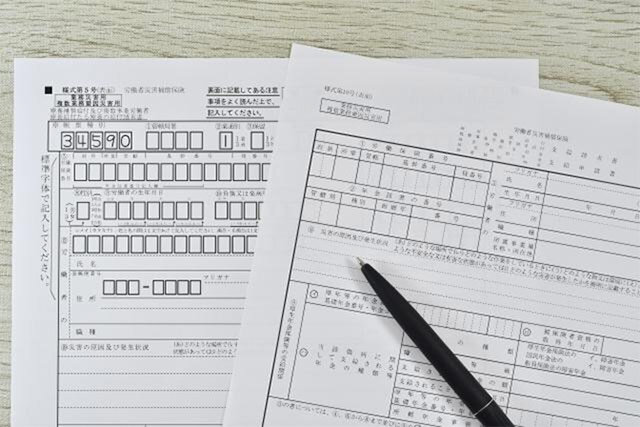
労災保険の給付を受けるためには、労働基準監督署へ申請が必要です。
労災事故が起きたときに焦らないよう、労災の申請の流れを確認しておきましょう。
労災の申請は労働者本人や家族が行うものですが、事業者の記入欄もあるため、事業者が代わりに作成して提出することが一般的です。
【1】従業員から労働災害の報告を受ける
【2】申請書を作成し、必要書類とともに提出
申請書は所轄の労働基準監督署や厚生労働省のホームページから申請書を取得します。
給付の種類によって申請書が異なるので注意しましょう。
提出先は所轄の労働基準監督署です。
複数業務要因災害の場合は、主に負荷を受けたと感じる就業先の管轄の労働基準監督署に提出してください。
【3】労災事故の調査、支給決定
労働基準監督署が労災事故について調査を行い、必要に応じて請求者や関係者に書類の提出や聴取がされます。
その結果、支給が決定すれば、指定した振込口座へ保険給付が支払われます。
療養(補償)給付による医療機関での療養については、受診した医療機関が労災病院・労災指定医療機関なら自己負担なしで療養が可能です。
労災申請と労災認定の結果を待たずに、先に病院にかかることも多いでしょう。
その際には、労災事故であることを申し出て受診してください。
労災病院・労災指定医療機関以外の病院を受診した場合は、労働者本人が医療費を一度立て替えて支払い、労災が認定されると立て替えた医療費が戻ってきます。
労災が認定されなかった場合は、健康保険の適用となります。
労災事故が起こったときには、状況の把握と労働者への補償のためにもできるだけ早く労働基準監督署へ報告を。
また、労災申請は給付内容によって請求権が発生してから2年または5年の時効があります。
原則として、時効を過ぎてしまうと給付を受けられなくなってしまうので注意しましょう。
2年:療養(補償)給付※、休業(補償)給付、葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付
5年:障害(補償)給付、遺族(補償)給付
※労災病院・労災指定医療機関で療養を受けた場合は現物給付のため期限なし
労災保険は正式名称を「労働災害補償保険」といい、業務や通勤を原因としてケガ、病気、障害、死亡などが起こった場合に給付が受けられる制度です。
1人でも従業員を雇っている会社は必ず加入しなくてはならず、会社に「雇用」されている人なら勤務日数や時間、雇用形態を問わず対象となります。
正社員だけではなくパートやアルバイト、日雇いなども対象ですよ!
業務を原因としてケガをした場合の医療費や休業補償、障害が残ったり亡くなったりした場合の年金や一時金といった種類があります。
万が一労災事故が起こった場合は、労働基準監督署へできるだけ早く報告し、労災申請を行いましょう。
社労士または労働基準監督署に確認し、適切な手続きをとってください。
会社の福利厚生として、役員や従業員のための労災の上乗せ補償を準備しておくと安心です。
神奈川県内の中小企業や個人事業主の方は、神奈川県福祉共済協同組合の傷害補償共済Ⅲもぜひご参考ください!